
どうも、初めましてさわくんです。中高引きこもりまくった結果、カウンセリングの極意に達し、以来人の闇に向き合い続けておりました。大学生のうちに3000人以上の心の闇を見たり、中高生向けの教材を出版し数千人の学びのあり方を改革した上で、クリエイティブの世界へ。
その人の心の闇の裏側に宿るエネルギーを駆使し、新たな文化創造を引き起こすお手伝いをするのが得意です。
プライベートですと、12歳上の嫁と12歳の娘と100人シェアハウスでアナーキーに家族生活していたりしてます。基本混沌としているのが心地いい人間です。良薬口に苦しと言いますが、僕の仕事はそういうものです。痛くても本気で変えたい何かがあるという方、お問い合わせお待ちしております。
<記事掲載>
幸福の解体新書(JDN連載コラム):https://www.japandesign.ne.jp/column/sawakun-introduction-1/
良い採用サイトは良い企業コンセプト作りから!(HR MAKER):https://www.youtube.com/watch?v=56xYp0DLIUM&t=626s
企業コンセプトを作って、会社を強くする(HR MAKER):https://www.youtube.com/watch?v=JZh70IS398c
採用にはなぜ「コンセプト」が必要なのか?(HR NOTE):https://x.gd/x8Q0P

原作者アメミヤユウが執筆した小説「RingNe」を有志が集い、現実世界に具現化させるプロジェクト。総勢200名のクリエイターを集め、『縦の異文化』を1日限りで顕現させました。

祭りを通して、地域のつながりを取り戻す共創DAOでの取り組み。第一弾の四国では、弘法大使がはじめた「88ヶ所巡り」を現代版にアレンジした「NEO88ヶ所祭り」を実施しました。

RULEMAKERS DAO(通称:RMD)は既得権益層やロビイストなど、一部の限られた利権、専門性に閉ざされたルールメイクの領域を一般の方々に開く為に実際にルールメイクの実施、育成、サポートを行う機関です。第一弾として「ソーシャルセクターの産業改革」を提言、骨太の方針に掲載されるなどの成果を挙げました。

弊社で制作した「(Q)reative」を基軸とした採用サイトなどの施策により、「文具・オフィス家具メーカー」といったイメージから 「既存の枠にとらわれることなく、自分なりの問いを起点にあらゆる領域で創造性を発揮し、未来を豊かにしている会社」への認知が取れ始めている一方、「仕事のどういった場面で(Q)reativeをしているのか」「(Q)reativeな行動とは具体的にどういうことなのか」学生の方々がイメージできてない状況がありました。そのため、「(Q)reative」に対する実感を持つことができるコンテンツ制作。コクヨらしい新規事業開発を立ち上げた責任者の方々に「(Q)reative」とは何かをヒアリング。インタビューを分析してくことにより、コクヨらしい新規事業開発16の要素を抽出、「(Q)reativeの発想の型を体得してもらう」1dayインターンシップへ昇華させました。

映像制作の過程を通してインナーブランディングをする。その過程で楽しみながら「企業の共通価値=誇り」を探れるボードゲームを作ってほしいと依頼を受け制作。数百のボードゲームを探究してきた知見とコーチングで人の想いを言語化してきた知見を組み合わせ誕生しました。

これまで自分が培ってきたコーチングの知見と、ランニングホームランのクリエイティブの知見を組み合わせ開発。従来のブランディング会社が常に帯同する形ではなく、自社の方向性を自社だけで意思決定できるようサポートするブランディングメソッドです。

テレビ一強時代が終焉し、誰もがクリエイターとして発信できる時代になった現代。
広告を中心とした「クリエイティブ業界」は大きな変革点にあります。
表現を極めることに加え、マーケティング、事業開発など、これまで専門性が分断していた領域を複合的に考えていく、新しいクリエイティブが求められています。
しかし、クリエイティブ領域の就活は旧態依然のまま。だからこそ、これからのクリエイティブ業界やそこに憧れる学生、若き才能が、次世代にシフトできる社会環境に変革すべく、「クリエイティブ就活を問い直す会」は発足しました。

コンセプチュアルに生きたい人々のために、コンセプチュアルなプロダクトを紹介するメディアです。時代の流れ的に、経済成長から社会課題解決思考へシフトする中、その次の時代にくるのが「コンセプト」だという予感のもと、立ち上げを行いました。
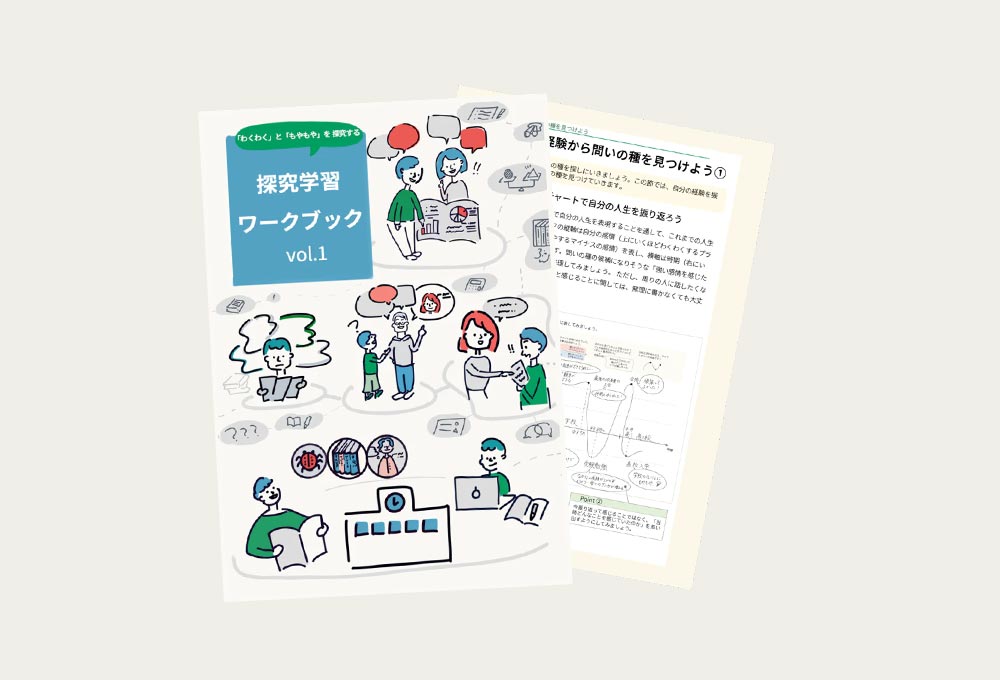
自分の人生を進める「問い」を見つけるためのワークブックです。実際に中高10校以上に導入されています。正解のない時代、答えを見つける力よりも、問いを見つける力が大切になってきます。そこで、問いを見つける過程を徹底的に言語化し誰もが自分の「問い」を見つけられる教材を作成しました。
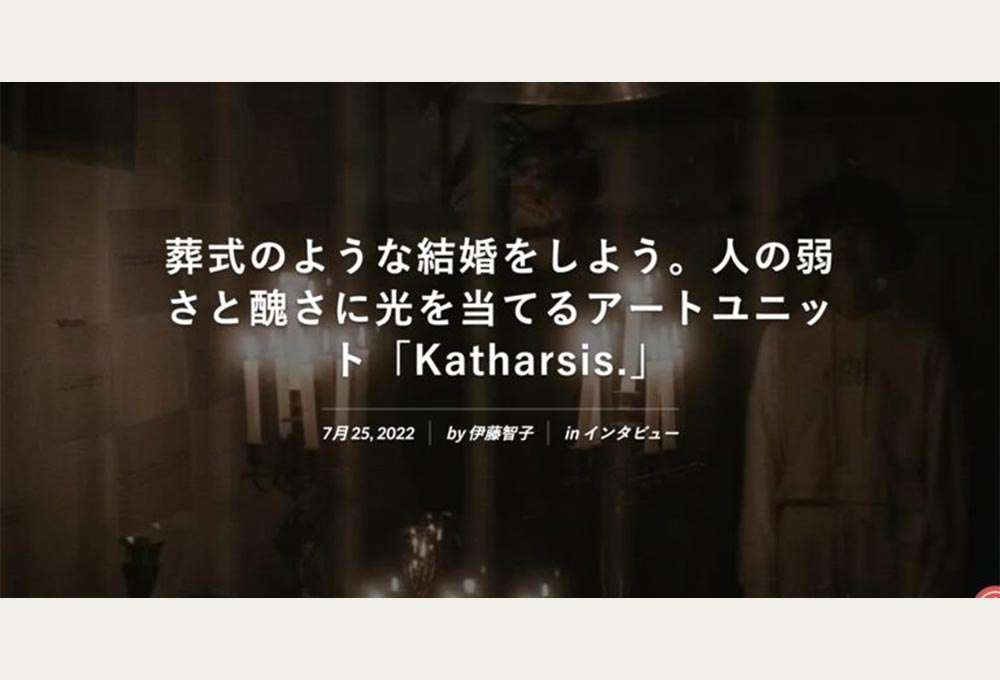
結婚をするにあたってせっかくなので自分たちの問題意識をアートとして表現しようということで生まれた婚葬式。結婚式と葬式という真反対の感情が生じる場所で、人はどのようにその場に参加するのかを問う社会的実験を行いました。